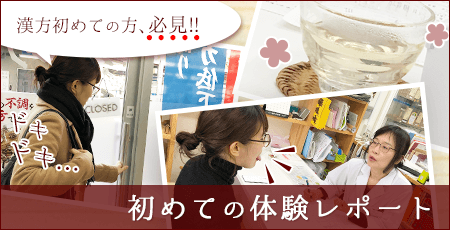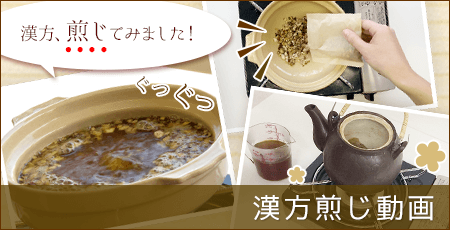冬の漢方
冬の季節

日本の冬は日照時間が短く夜が長くなり、厳しい寒さに加えて乾燥が強くなります。
陽のパワーが弱く、陰のパワーが強くなります。私たちの体は寒さから身を守り、生命力を内に集めるために陽気が内部に集まります。
そして、寒い夜に孤独になって考え込むと、気持ちが暗くなってうつになりやすくなります。我々はできるだけ、日中に太陽に向かう時間を作る必要があります。
漢方の古典「黄帝内経」では、冬は「閉蔵」とされ、すべてが閉塞して陽気を外に出さなくなる季節とされています。草木は枯れ落ち、穀物は蔵にしまい込まれ、動物は冬ごもりするのです。
そしてこの季節には早く眠り、日の出に合わせてゆっくりと起きる。寒冷を避けて暖かに保ち、汗をかくなどして陽気を失ったりすることがないようにする。
そうしないと腎を傷めて春に障害がおこるとされています。
冬に多いトラブルから身を守るために

冬は、まず保温することが大切になります。寒さから身を守るためには、衣服の選び方も大切です。
厚着することも寒さ対策になりますが、重ね着をすると体の周りに空気の層を作るので、保温力を高めるため、寒さ対策に効果的です。寒さから身を守ることが大事です。

そのためには体の内側から温めてくれる食物を摂ることも心がけねばなりません。
できるだけ、体を温める食品を多くするよう心がけます。人参や蕪、大根などの根菜類は体を温めてくれます。
それに対してサラダなどに使うレタス、キュウリ、トマトなどに南国で取れる果物は体を冷やします。ただ、体を冷やす食品でも、生食ではなく、煮たり、焼いたり、ゆでるといった調理で、食性を変えることができます。

1年で昼が最も短い冬至(12月21日、または22日)には1年間の陰が極まり、続く新しい1年間の陽のパワーが生じる転換点になります。つまり、この日から「春」へと向かっていくわけです。
ところが、その反面、冬の寒さはピークになります。ですから、さらに冬の養生を続けなくてはなりません。このような訳で、寒い冬は体を温めるために肉類など、高タンパク質のものを多く摂ることが多くなります。
しかし、高タンパク質のものを食べすぎると内臓、特に胃腸、肝臓、腎臓に多くの負担がかかっていきます。春を迎える前の頃に胃腸の不調を感じる人が多くなります。この時期には、むしろ積極的に温野菜、豆類、雑穀といった温かい野菜を中心とする食事にして胃腸の調子を整えていくようにします。
この時期、2月3日の節分に食べられる大豆は植物性のタンパク質が豊富で栄養補給に優れています。また大豆に含まれるイソフラボンは女性ホルモンのエストロゲンと似た働きをするので、特に更年期女性には自律神経の安定にも役立ちます。